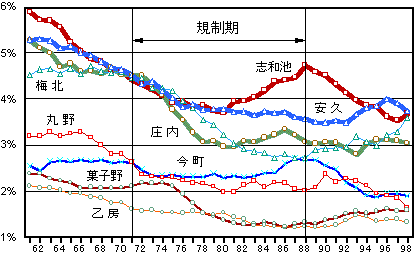
まちづくりでよく話題となるテーマの一つが線引き(区域区分)です。この制度は、「新都市計画法」と呼ばれる1968年の都市計画法大改正で生まれたもので、都市が無秩序に拡大するのを防ぐことと目的に、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、調整区域においては一般市民の住宅建設等を厳しく制限するものです。新都市計画法は、すべての都市計画区域で「線引き」を行うことを目ざしつつも、当面は都市が無秩序に拡大していくスプロール問題の大きな都市計画区域を国が指定し、そこで規制を行ってきました。線引き制度は、各種ある都市計画制限の中でも最も厳しいもので、とくに地方都市では「市街化調整区域では一般の住宅が建てられないため、人口が減少して困る」という副作用が問題とされ、「線引きを廃止したい」という声も出されるようになっていました。地方分権への流れの中で「線引き」も見直されるところとなり、2000年に行われた都市計画法の改正で、三大都市圏を除き、線引きを実施するかどうかを決める権限が都道府県に与えられました。そこで、この機会を利用して線引き廃止へ踏み出そうと考えているところもあるようです。その一方で、1998年と2000年の都市計画法改正で、市街化調整区域で一般住宅を建設できる道が拡大されたことに注目し、線引き導入や、線引きを維持したまま柔軟にまちづくりを進めることを考える都市も出てきています。21世紀に入り、地方では人口が増加から減少に転換し、線引きの意味が問い直されるようになっている現在は、市街化区域と調整区域の扱いを考える重要な時期です。
これまでに線引き(区域区分)を廃止した都市計画区域はいくつかありますが、その代表格が、宮崎県の都城広域都市計画区域だと思います。現在と違い、当時は区域区分の実施を決める権限は国(建設省)にあったので、1987年1月8日の建設省都市局長の通達を根拠として作業が進められ、1988年4月22日に都市計画区域全体として線引きが廃止されました。
線引き時代に都城高専に勤務し、都城市に住んでいた私は、当時の状況を詳しく知っているので、線引きが廃止されて10年が経過した1998〜1999年に調査を行いました。調査の結果、行政や市民が線引き廃止に期待したのとは全く逆の現象も生じていることを発見し、驚きました。そこで、都城で生じていた事態を簡単に紹介し、私なりの提言を述べさせていただくこととします。同時に、線引き制度が誕生する根拠となった宅地審議会の第六次答申と、新都市計画法によって誕生した都市計画中央審議会の初の答申である線引きに関する答申も掲載いたします。じっくり第六次答申を読むと、その主眼は大都市問題にあり、当初は地方都市は視野に入っていなかったことがわかります。都市計画法改正を審議した建設委員会の会議録も詳細に調べましたが、答弁で言及されているのは、せいぜい仙台や北九州という地域の中心的な機能を受け持っている大都市までです。新都市計画法案作成の段階で、地方都市についての検討が不足していたことは残念です。今後は、都市計画の地方分権を実質化するためにも、都道府県や市町村の知恵を生かし、各地域の実状にあった運用が模索されていくことを願っております。
(2008.12.29更新)
2002年1月までは、このページを「コンパクト都市と線引き」と名づけていました。都市が郊外へだらだらと拡散するスプロール現象は、まちづくりにとって古くて新しい問題で、現行の都市計画制度の下でこの動きを止められるものは「線引き」しかないと考えたからです。しかし、「コンパクト都市」の定義は曖昧で、人によってイメージが違うことを発見しました。「私が考えていたコンパクト都市は、他の方がコンパクト都市という言葉でイメージするものと違う」ので、ページのタイトルから「コンパクト都市」を削除することにしました。昭和30年代頃までの都市は、市街地に様々な機能がコンパクトにまとまっていました。しかし、交通の発達によって「距離」が克服され、都市は爆発し、郊外へ郊外へとスプロールして拡散しました。このような都市の爆発を招いた最大のものは、車の普及(モータリゼーション)です。「牛乳1本買うにも車で出かけないといけない都市」はどう考えても行き過ぎで、「歩いて暮らせるまちづくり」を目ざす必要があります。現に、ドイツでも、90年代に入り、"stadt um kurze weg" 、つまり「短い距離の都市」が「まちづくり」のスローガンになっています。
多くの人が「コンパクト都市」と言っていますが、その定義はいろいろです。私がイメージしていた「コンパクト都市」は、高層ビルが林立する都市ではなく、公共交通がまだ強かった昭和30年代までの日本都市の状況に近いものです。もちろん、当時の都市を現在と比較すると、いろいろ欠点もあります。現代都市の長所を伸ばすと同時に、過去の都市が有していた長所も併せ持つ都市、これを示す言葉をご存じの方、是非教えて下さい!
規制緩和が叫ばれるなかで、1987年1月8日に出された建設省都市局長の通達が、線引きを廃止するための3条件を示しました。この通達をもとに、既にいくつかの市町村では線引きが廃止されています。ただ、通達に基づいて都市計画区域全体として線引きを廃止したのは、都城市と周辺4町から成る宮崎県の都城広域都市計画区域だけです。
宮崎市で育った私は、子供の頃から時々都城の親戚宅を訪問していたので、昭和30年代の活気にあふれた都城の状況を覚えています。大学を出て、1972(昭和47)年に就職した先も都城市でした。しかも、都城市に住み始めて、最初に取り組んだ研究がこの「線引き問題」です。それは、都城市が当時かかえていた都市計画に関する課題のうちで、最も重大なものだと感じられたからです。
結局、私は福島に移るまでの16年ほどを都城市で過ごすこととなりましたが、この期間は、都城広域都市計画区域に線引きが行われていた時期とほぼ重なります。実は、私は、線引きの廃止時には、都城市都市計画審議会の委員を務めていました。廃止を決める審議会は、授業と重なっていたため、欠席しました・・・線引きの重要性と同時に、問題点もよく知っていたので、出席できない時間帯に会議があると知り、ほっとしたことを覚えています。
線引き廃止後10年が経過した時期に、地元で論じられた問題点、ならびに人口変動を中心として調査を行い、結果をまとめ、1999年の都市計画学会で発表しました。都城市で最も大きな問題とされたことは、市街化調整区域で過疎化や高齢化が進行するという点です。これは、私が70年代に行った調査結果をもとに指摘していた点とも一致します。問題は、線引きの廃止で、調整区域で進行していた過疎化や高齢化は改善されたのか、という点です。その結果をはっきり示しているのが、次の図です。この図は、校区内に市街化区域を有しない小学校の生徒数が、市全体の小学生数に対して占める比率の変化を示したものです。都城市議会では、線引きに関連してよく小学校の生徒数が取りあげられ、調整区域の生徒数が減少していることが重要な問題として論じられていました。
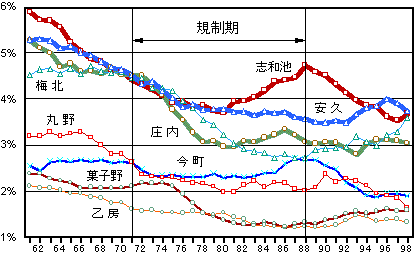
上の図から、つぎの3つの点を読みとれます。
以上のように、生徒数は線引きの影響だけで増減しているわけではなく、市の中心部からの距離や、旧役場所在地かどうかも関係しています。とくに、中心部から離れた小学校では、規制緩和後にかえって生徒数が減少している点は重要です。年齢別人口を検討した結果、これらの地域では線引き廃止後に高齢化の進行が加速されたことも確認できました。以上の事実は、議会や行政が線引き廃止に期待した効果は必ずしも生じず、かえって『線引きを続けていた方が、線引き廃止に期待した効果が得られていた部分もあり、予測とは逆の現象も生じている』ことを明瞭に示しています。
線引きのあった規制期にも調整区域の人口が維持されたのは、規制期に市街化区域の拡大がほとんど行われなかったため、市街化区域に住居を求めることが次第に困難になり、血縁関係を活用し、「許可を得るのに手間はかかるが、育った土地に住もう」と考えて行動した人が多かったためです。規制緩和は、「住む自由」を与えることにより、人口の維持を図ろうと考えられたものでした。ところが、規制緩和は、「住む自由」と同時に、「どこにでも住む自由」、つまり「住まない自由」まで提供してしまったのです。こうして、結果的に、各地区の立地条件、とくに都市中心部からの距離が影響し、遠隔地では過疎化が加速される結果となってしまいました。
このような状況が生じるとは、私を含め、誰も予想していませんでした。私が線引き廃止の10年後に行った調査による最大の成果は、調整区域の規制は、人口の流入を困難にする作用と同時に、市街化区域の開発余地の減少に伴い、人口が中心部に吸い上げられるのを防ぐ機能を有しており、市の中心部から離れた地域における「人口減少の防止」に貢献していた、ということを発見した点にあります。
以上の都城線引き調査結果は、『日本都市計画学会論文集』34号(1999年11月発行)に「都城都市圏における線引き廃止への経緯と効果」というタイトルでまとめておりますので、詳細についてはそちらをご覧下さい。
以上は、都城市の区域区分が廃止されてから約10年間の動きを追ったものです。そこで、その後の動きを含め、統計データを検討しておきたいと思います。なお、都城市は2006年1月1日に山之口町、高城町、山田町、高崎町を合併(平成の大合併)し、面積が約2倍になりましたが、以下はこの合併前の都城市に関しての記述です。
まず都城市の人口変動ですが、線引き廃止を目指していた当時の坂出市のホームページには、線引き廃止が都城市の人口増加に寄与したかのような次の記述がありました。
人口については、線引きを廃止した前後の6年間は減少を続けていましたが、平成3年以降、大学誘致により学生が増えたことや民間企業の進出などに伴い増加に転じ、平成2年の13万153人から平成10年には13万3367人と、約3200人が増えました。特に旧市街化区域の周辺に位置する地域では,昭和63年から平成9年までの増加率が50%を越えるところもあり、30〜40代の世帯を中心に増加しています。しかし、私が調べたところによると、都城市の人口変動に最も影響を与えているのは、18歳人口の流出とその回帰です。都城市には高等教育機関が少ないので、高校卒業と同時に県外へ多くの人口が流出していきます。流出から数年以上経過した後になると、大学を卒業したり、あるいは地元で職を得ようと、流出した人口がかなり戻ってくるわけです。1990年前後の人口減少は第2次ベビーブームのピークが18歳に達したためであり、数年後に人口が回復することは初めからわかっていました。下に示したのは、都城市と、その東に隣接する三股町についての、線引き期前後の人口変動です。
| 国勢調査人口 | 都城市 | 三股町 | ||
| 年 | 人口 | 変化率 | 人口 | 変化率 |
| 1965(昭和40)年 | 118,583 | -2.4% | 14,803 | -2.9% |
| 1970(昭和45)年 | 114,802 | -3.2% | 14,699 | -0.7% |
| 1975(昭和50)年 | 118,289 | 3.0% | 15,789 | 7.4% |
| 1980(昭和55)年 | 129,009 | 9.1% | 17,713 | 12.2% |
| 1985(昭和60)年 | 132,098 | 2.4% | 18,832 | 6.3% |
| 1990(平成2)年 | 130,153 | -1.5% | 21,011 | 11.6% |
| 1995(平成7)年 | 132,714 | 2.0% | 22,941 | 9.2% |
| 2000(平成12)年 | 131,922 | -0.6% | 24,056 | 4.9% |
| 2005(平成17)年 | 133,062 | 0.9% | 24,545 | 2.0% |
都城広域都市計画区域に線引きが行われたのは1970年11月で、廃止されたのは1988年4月です。この表を素直に見ると、「減少していた人口が、線引きの結果として増加に転じたが、その後の線引き廃止で再び減少した」と理解できるのではないでしょうか。しかし、実際は「第1次ベビーブーム世代の市外流出によって60年代に人口が減少したが、その後その世代が30代となり、人口の回帰で増加に戻った。90年前後は第2次ベビーブーム世代の流出で再び減少傾向となり、その世代が30代になって再び増加に転じた」だけだと思います。なお、1990〜95年に人口が2千人以上増加しているのは、1991年に宮崎産業経営大学の経済学部が開校したのが主因だと思います。
一方、隣の三股町は、第1次ベビーブーム世代の流出による人口減少は認められますが、線引き廃止期と重なる第2次ベビーブーム世代流出の影響は見られず、逆に高い増加を示しています。都城市から見ると、三股町は「都城市の郊外」に位置していて、都城高専の先生にも、「三股に持家を建て、都城市内の借家から移転した」という人が何人もいました。線引き廃止の影響で人口が増加したのは都城市よりも三股町の方で、とくに増加が著しいのが若年人口です。都城市に接する6町(三股町、山之口町、高城町、山田町、そして鹿児島県の財部町と末吉町)の国勢調査人口を見ると、1985年までは増加する例もありましたが、1985〜1990年、1990〜1995年、1995〜2000年のいずれの期間も、人口増加が見られるのは三股町だけです。周辺の町でも、都城市の旧調整区域と同じく、線引きの廃止が人口減少につながるという状況が生じていたものと思われます。
 | |
| 南から見た明和小学校。手前は農業振興地域で「農用地」とされているため、市街化が行われていない。 | |
 | |
| 明和小学校の校庭から東を眺める。小学校の用地はもちろん、その東側約100mも旧調整区域で、都市計画税は非課税である。 |
では、上の折れ線グラフに示した、校区がすべて調整区域だった8小学校はどうなっているのでしょうか。小学校の位置によって少し違いがありますが、その後もわずかづつ生徒数の減少が進んでいます。そこで、8小学校の生徒数を合計し、市全体の生徒数に対する比率を計算してみました。5年ごとの結果を示したのが、下の表です。なお、学校別のグラフは、こちらにあります。
| 年 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| 生徒数 | 4,568 | 3,487 | 2,672 | 2,564 | 2,665 | 2,424 | 2,051 | 1,804 | 1,628 |
| 比率 | 29.0% | 27.1% | 24.2% | 20.8% | 21.2% | 21.5% | 20.5% | 20.4% | 19.6% |
| 〃変化 | − | -1.98 | -2.87 | -3.35 | 0.31 | 0.36 | -0.99 | -0.12 | -0.86 |
都城市か線引き廃止を求めた最大の理由は「市域内の人口バランスの確保」にあり、この点は、他の都市においても秩序ある発展のために非常にポイントです。したがって、人口バランスを確保するためには、どのような制度が望ましいかという点を考えなければなりません。同時に、各地で問題となっている中心市街地活性化や、あるいは伝統的な問題であるスプロール防止も視野に入れた対応が望まれます。都市計画権限のかなりの部分が地方に移され、地方の現状を見据えた対応が可能となった現在、線引きに関し、どのようにまちづくりを進めていくことが考えられるのでしょうか。
都城で線引きが大きな問題となったのは、線引きの実施にあたり、線引きに関する都市計画中央審議会の答申を根拠に、地方都市においても市街化区域に対しても60人/ha以上の人口密度を求め、市街化区域の最低規模として50haを設定したことにあります。この方針は、大都市圏のことだけを重視し、固有の歴史と伝統をもつ地方の実状を考えないものであった、と言わざるを得ません。
その後、都市計画法の運用は若干緩和され、40人/haを基準にしたり、20ha前後の市街化区域を設定する道も開かれるようになりました。さらに、1998年の改正では、市街化調整区域に地区計画を定めることで建築行為を許可する道(第34条8の2号=現10号)が開けました。そして、2000年改正で、法第34条に8の3号(現11号)と8の4号(現12号)が追加され、条例を定めることで調整区域に建築を認める道ができました。そこで、市街化区域の設定、調整区域の地区計画、そして調整区域への条例をどのように活用していくかについて、提言を述べたいと思います。
問題のひとつは、対象範囲が図で明示していない条例が主体であるため、建築に伴って連たん範囲が拡大し、俗に「錬金術」と呼ばれている現象が生じることです。50戸の連たんが基準になるので、「建物を建てられないはずだった土地に、周辺に他の人が建物を建設した結果として建築が可能になる」こととなり、土地利用行政への不信を招くことが大きな欠点です。また、距離を重視して運用すると市街化区域に近い集落から順に市街化が進みますが、すべての農業集落が市街化に適しているとは限りません。たとえば都城の場合、旧合併町村の中心部と市街化区域の間に、ほとんどの農家が牛を飼育している集落がある部分がありました。もし市街化区域に近い集落から都市住民が居住すると、畜産公害が問題とされ、落ち着いて営農できなくなります。幸い、都城では宅地化が旧市街化区域周辺の畑作地帯に集中し、畜産公害はほとんど問題とされていませんが、集落によって営農状況や市街化への適否が異なる以上、市街化区域からの距離にとらわれずに判断すべきであると考えます。
もうひとつの懸念は、建築物の用途や形態を厳しく制限する運用が多いことです。現実の農村部では、混住化と兼業化が進み、用途はかなり多様化しています。しかも、条例で専用住宅の建築しか認めなくしても、34条1号で農機具修理工場や精米所が認められたりするので、用途を厳しく制限する環境上の効果はあまりありません。調整区域にある農業集落の活性化には住宅建設と産業発展の両面があり、地方都市では、市街化区域のベッドタウン化より、産業面の役割が重要です。だから、良好な住環境が得られると信じて都市住民が流入した場合、農業集落の自律的な発展が妨害され、かえって問題となります。調整区域で低密住宅地を実現したい場合には、地区計画を用いるべきでしょう。
現行の都市計画法によると、一旦建築を認められることとなれば、農業振興地域の白地地域であればどこでも同じように扱われ、既存集落近傍かどうかが考慮されません。既存集落を核として発展させることは、このような現状と比較しても望ましい方策であり、宅地審議会第六次答申が述べているスプロール的開発と、既存集落の秩序ある拡大とを区別することに通じるはずです。都城を教訓に、1998年や2000年の都市計画法改正で生まれた可能性、つまり地区計画と、2種類の規制緩和型条例を活用し、集落人口の維持・コントロールを考えることで、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する(都市計画法第1条)」ことを願いたい、と思います。
1968年の都市計画では、すべての都市計画区域で線引きを行うことが建て前となっており、線引きを行っていないところは「猶予されている」という意味で「未線引き」都市計画区域と呼ばれていました。しかし、2000年の都市計画法改正で都道府県が線引きの有無を判断することとなり、「非線引き」都市計画区域に変化しました。それでも、線引きの有無で都市計画の中味が大きく異なり、両者の間に断絶があることは変わっていません。
線引きが行われていない都市では、周辺部の集落への人口流入が可能です。線引きが行われる以前は、地方都市の周辺にある集落も、この種の人口流入で維持されていました。しかし、「線引き」がこの流れを人工的に断ってしまいました。純粋な農村から脱し、一般市民との混住化が進みつつあった既存集落が、ただ「人口規模が大きい都市の周辺にある」ことだけを理由に市街化調整区域とされ、発展が止められたわけです。この結果、学校に複式学級が導入されたり、店も消えて遠方まで車で買い物に行かなければならなくなる事態が現れています。このような状況は、都市計画法が目的とする「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する(都市計画法第一条)」ことに明らかに反しています。現在、わが国では、「このままではやがて人口が減少するので、子供を生みやすい環境を整備しなければならない」と、検討が進められています。そのような国土の一部に、しかも中規模以上の都市の周辺に、人工的に枯渇されつつある集落が多数存在することは、とても納得できません。この事態が、調整区域の規制が次第に骨抜きにされたり、線引きの廃止を求める地方都市が見られる原因となっていると思います。
これからは、法改正で提供された地区計画や条例を活用し、集落の維持を可能とすべきです。私は、運用によって「線引き」都市計画区域と「非線引き」都市計画区域の間にある断絶を埋め、両者を連続したものにすることが理想だ、と考えています。連続していたら、各市町村が、その置かれた条件に応じ、「線引きの長所」だけを享受することを目ざして、「うちはこのあたりのレベルで線引きを導入しよう」と足を踏み出すことができるからです。
最後に、線引きの長所として見逃せないものに、中心市街地の活性化があることを述べておきたいと思います。線引きを嫌って都市計画区域外に流出する世帯が見られることを理由に、「人口が減って商店街が衰えるのを防ぐために線引きを廃止したい」と考えるとしたら、とんでもない間違いです。線引き廃止から10年後に都城の中央通りを訪問した私が見たものは、予想以上に疲弊した商店街の姿でした。道路の整備が進み、車が交通の中心を担っている都城市では、中央通りで若い世代が買物を行っている姿を見出すのは困難です。中央通りで若者が見られるのは、中学校や高校の生徒が通学の途中に寄る程度、と言っても言い過ぎではないかもしれません。
もちろん、中央通り商店街でも対抗策を考えています。中央通りの一部では土地区画整理に取り組まれ、土地区画整理による基盤整備の進行にあわせて、シビックコアや立体有料駐車場などの施設も建設されました。また、地方検察局、地方法務局、税務署、統計情報事務所、労働基準監督署、公共職業安定所の6機関をこの街の中に持って来る国の地方合同庁舎も完成しています。もちろん、商店自体も頑張って取り組み、1999年にはオーバルという中庭のある回遊型共同店舗がオープンし、2002年には協調建てかえ方式でcプラザも完成しました。既存デパートのそばには、そのデパートが建設したモールもできています。
(提言)
断絶した制度から連続した運用へ
ただ、ここで注意してほしいことが2つあります。ひとつは地区計画の自由度の高さが、逆に問題を生む可能性もあることです。「市街化調整区域に地区計画を定めるに当たっての最低必要な要件」は定められていません。だから、もし不十分な地区計画が広がって建築が許可されていったら、調整区域の田園的な環境が破壊され、無秩序な町が出現することとなります。だから、都道府県が都市計画区域のマスタープランにおいて調整区域地区計画への考えを示したり、市町村マスタープランで位置づけを明らかにしておく、等の手法が望ましいと思います。もちろん、市町村が地区計画を定めるには、都道府県知事と協議し、同意を得ることが必要で、円滑な制度運用のため、国は、都道府県が同意にあたっての判断指針等を作成することを勧めています。
注意してほしいもうひとつの点は、「優良田園住宅」との関係です。調整区域に地区計画を定めることで建築を可能にした1998年の都市計画法改正は、「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」と同じ国会で行われました。しかし、これを根拠に、地区計画に対して「優良田園住宅」レベルの開発を求めることには疑問があります。もともと「優良田園住宅」では既存集落の自然な発展は除外されており、低密な市街地を義務づけています。私は、都城市周辺部での生活を通じ、地方都市における既存集落の自然な発展は望ましいものであり、既存集落を核として市街地を徐々に拡大していくことは「スプロール」とは言えない、と考えています。「優良田園住宅」は調整区域の建築が厳しく制限されていた時代の遺物であり、都市周辺部においても「庶民が住める普通の住宅」の建設を許容すべきだと思います。
「市街化区域に隣接し、又は近接し」という言葉を表面的かつ厳密に解釈すると、市街化区域から一定の物理的距離内にあることを指標とする運用が考えられます。旧既存宅地条項の運用を市街化区域から1〜2kmに制限している都道府県が多いことが、この方式の正当性を示しているように思えます。
しかし、旧既存宅地条項と異なり、今回の条例の指定範囲では全域で住宅を建築できます。たとえば市街化区域から1〜2km以内にある集落の外郭を指定した場合、かなりの人口増加が見込まれるので、市町村は現在以上に学校建設などの整備を強いられかねません。これでは、衆議院建設委員会における法案審議の際に建設経済局長が説明した「市街化区域に隣接、近接するというものでございますけれども、これにつきましては既存の公共施設が利用可能だということで、新たな公共投資をほとんど要しないようなところだ、こういうような性格であります」という説明に逆行し、都市計画法が目ざしているスプロール防止の趣旨にも反します。だから、距離だけを考えた運用には問題があります。
もうひとつの運用方針は、上記の建設経済局長答弁の趣旨を生かし、公共施設の余裕を重視する方法です。調整区域の既存集落には、学校に余裕があり、商店もあり、また郵便局などの施設も整備されているところが少なくありません。このような既存集落こそ、近接・隣接条例を生かす適地です。しかも、これら既存集落は都心との交通の便も良く、物理的な距離はあっても、機能的・心理的には市街化区域に「近接」しています。現に、1974年の国会における都市計画法改正の審議で、議員から旧既存宅地条項を追加するという修正提案が行われた際に、「市街化区域に隣接し、又は近接し」という言葉の解釈について意見を求められた都市局長は、次のように答弁しています。「実際にはそう奥深い調整区域というものが設定されておるわけでありませんから、まあ、川で断絶されているとか、断崖があるとか、あるいは道路が通じていないとかいうようなことがない限り、市街化調整区域の一番端までいきましても、市街化区域の境目からそう遠いともいえない。歩けば遠いにしても、日常生活圏としては入るような気もいたします」。
以上のような考えから、私は「地方都市における土地利用規制と線引き問題」(『都市問題』第92巻第8号、2001年8月)で、公共施設の余裕を重視して近接・隣接条例を活用することを提言しました。しかし、その後の近接・隣接条例の運用状況を見ると、物理的距離を重視した使われ方が主体となっており、いくつか問題が懸念されます。
また、形態規定として、大半の建物が1〜2階建てであることに配慮した制限は必要でしょうが、市街化を困難にするために建ぺい率や容積率を厳しく制限することは疑問です。1968年法による線引きが登場する以前は、郊外の市街化を抑えようと、厳しい形態制限を課すケースが各地に見られましたが、この手法では市街化を抑制できず、かえって違法建築の温床となる例もありました。厳しい建ぺい率や容積率の制限は1968年以前への後退であり、形態規制はあくまでも集落や市街化区域の状況を基礎に定めるべきです。
ところが、この条例の運用状況をみると、これまでの「市街化を促進しない」として個別に認められてきたよりも幅広く用いている例があります。市街化区域内へいくら建築しても農村集落の活性化はできないわけですから、私は、「農村集落の活性化」を目的に建築を許可するという筋道を立てれば、この条例の対象にできるはずだ、と思っています。
さらに、2008年末には、駅のそばにあった旧ダイエーが、店舗面積約2万4千平方メートルと倍に拡大し(商業面積は約3万3千㎡)、「イオンモールmiell都城駅前店」として再出発しました。休日になると、周辺の道路は遠方から来た車で混雑します。都城市は、戦後何十年もかけて土地区画整理を進め、道路網がよく整備されていますが、それは都城市民のためであり、イオンが遠方から車で客を集めるためではなかったはずなんですが・・・。ただひとつの救いと考えられるのは、「イオンモールmiell都城駅前店」は町の中にあり、歩いて買物に行ける市民が多いことでしょうか。聞いたところによると、イオンモール担当者の方も、こんな町の中に建設するのは初めてだ、とおっしゃっていたそうです。いずれにせよ、線引き廃止都市・都城市は、商業の点で大型店の占有比が極端に高い都市へと展開してしまったようです。
思うに、問題は区域区分の有無ではなく、「住みよい都市」かどうかということです。区域区分の有無にかかわらず、さまざまな手法を活用して、住みよいまちづくりを追求することが必要ですが、都城市や、2004年に廃止した高松市・坂出市・丸亀市には、率先して行った区域区分廃止がどのようなまちづくりにつながったのかを、具体的に情報発信していく責任があると思います。
(2008.12.29更新)
 トップページへ戻る
トップページへ戻る